
このページは当学会設立時の2001年から2010年までの第一期における年次大会の内容概要のアーカイブです。資料的位置づけにあり量も多いため文字の大きさを小さめにしてあります。
2001年11月23日(祝金)9:30 - 18:00 ・ 24日(土)9:15 - 20:00
かずさアカデミアパーク(木更津)
【口頭発表】
構想科学への試論/”メンタルモデル論”を越えていかにして構想の生成プロセスを理論化するか
匠 英一(認知科学研究所)
構想の生成プロセスを「活動理論(U.Engestrom)」とナレッジマネジメントの諸説(D.Leonard)から理論モデル化することで、構想科学の枠組みを提案する。 とくに、構想とビジョンの違い、創造的摩擦、メンタルモデルなどをキーワードに、ビジネスモデルの構想プロセスを分析するための基本視点と実践事例を紹介し、今後の構想科学に向けた試論を述べる。
参考文献として、92年春期・経営情報学会匠論文「発想・問題解決支援システムの認知デザイン論」がある。地域生活ソリューション事業:その構想と戦略
加藤誠也(株式会社ダイナアーツ・インターディベロップメント)・ 高谷周司(松下電器産業株式会社 家電流通本部)
成熟家電の雄たる企業に見る新価値創出への構想と取り組み: 新たな時代に、社会・地域生活の新たな要請に対応する、新たな地域のリテール・ネットワークづくりを目指して、信頼の証としてのコーポレートブランドを活用し、自前主義を超えて地域の要請に呼応する新たな商材・サービスを展開する地域密着型の生活ソリューションビジネスの創出・事業化に向けた活動を紹介し、これからの事業企画への示唆を抽出・検証する。
沖縄米軍基地跡地を利用した国際航空宇宙港構想に関する研究
高田尚樹(独立行政法人 産業技術総合研究所)
本報では、沖縄県の米軍基地跡に宇宙往還機の離着陸機能を持つ国際空港を建設する構想、OASIS Planを紹介する。OASISとは、沖縄航空宇宙国際ステーション、および沖縄航空宇宙アイランドの略称である。本構想は、人工衛星打ち上げや地球低周回軌道飛行および弾道飛行よる宇宙観光等の宇宙環境の商業利用を推進し、航空宇宙産業の発展と新規雇用の創出により、沖縄およびアジア地域の経済発展と平和の推進を目指す。
ホームスクールも認められる社会へ
日野公三(日本ホームスクール支援協会)
アメリカの学校では、学校選択の自由がかなり保障されており、ホームスクール(学校へ行かない自由)も50州全てで保障されている。アメリカのホームスクールの意味するところは、以下の諸点にある。学校中心の価値観の相対化、学校選択の自由(の保障)、教育と親の責任(の明確化)、安全な学習の場(の提供)、ニューエコノミー時代のあるべき教育である。アメリカでは支援団体の活動によってホームスクールの市民権を獲得してきたが、私共もそれにならい、2000年7月に日本ホームスクール支援協会を設立した。わが国も親の教育権としてのホームスクールも認められる健全な社会へ移行すべきだ。
公共圏から交響圏への転換構想 —あらたなる公教育圏の可能性—
端田哲郎(特定非営利活動法人 NeoALEX社会構想研究院)
17世紀後半の「カフェ」では貴族や知識人たちがつどい、「小さな討議」をしていたという。しかし、現代の「カフェ」においてそれがおこなわれることは、日本はもとよりフランスでさえない。その原因はどこにあるのか。本発表は、現代の日本のカフェが「市民的公共圏」として機能しない原因と、その代替案とされる「電子空間の公共圏」の問題をあきらかにし、あらたな「市民的公共(交響)圏」の構想を提示したい。
社会構想の絶対性
高橋健太郎・橘内潤(宮城大学 事業構想学部)
今日、社会構想はあたかも個人の自由な創造領域であるかのように思われている。しかし、実現に際しそれは個人の創造領域を超える。他者の意識改革と役割を強制し、社会全体を支配する原理となる。つまり、社会構想は絶対性を伴うものなのである。以上のことを青年、民間会社、自治体、宗教団体、国家の社会構想のあり方から検証する。
高齢社会におけるライフスタイル創造型介護
荒川創・佐藤祥子(地域文化創成社 爽風白露)
日本は高齢化が急速に進み、福祉が大きな課題となった。特に介護福祉のニーズは非常に高まりつつある。確かに福祉ニーズに応えることは福祉を必要とする者にとって重要なことであるが、福祉事業がこれからの社会の大きな鍵を握る以上、ニーズに従うだけの事業では社会的創造の可能性は期待できない。そこで価値観のパラダイムシフトした社会的幸福概念とそれに基づく新事業が必要と思われる。本発表ではそれを「閑暦抄」と定義し、閑暦抄事業の社会的影響を論じることとする。
喫煙行動における心理的作用の歴史と構想
加藤裕也(宮城大学 事業構想学部)
昨今、タバコほど賛否両論あい分かれて激論が戦わされている商品はあるまい。このような中でタバコをめぐる現状を冷静に見つめ、“構想”していくためには、タバコの地球規模の歴史を知る必要があるだろう。世界中のあらゆる地域が、このドラマを演じる役者である。そして、このドラマに幕は引かれていない。本発表では、Jordan Goodman著「タバコの世界史」などを参照に、タバコの魅力、なぜ人はタバコを吸い続けるのか、一考察を施す。
金原省吾: 構想のエステティーク
佐々木弘・上西普子・麻地理恵(特定非営利活動法人 NeoALEX高等教育研究院)
20世紀前半に「構想の研究」を著した東洋美学者金原省吾はその研究に何をみたのか。著者は構想を人間の認知過程の一段階にあてはめ、創作における構想段階の重要性をといている。本研究では、写生や詩文の綴りかたを俎上にのせた構思を考察する。そこにみられた「観る働き・描く働き」という作用により、創作がいかにして完成への過程を辿るのかをひもとく。さらにこの構思に基づき、直近に打ち出された構想事例を考察する。
身体技法のもうひとつの探求法 〜身体技法研究同志会の歩み〜
竹内光芳(日本光電株式会社)
従来、身体の様々な技法の習得にあたっては、その「型」の伝承が主軸となってきた。また、認定される段位や、試合形式による順位が、その到達度を示すものとされてきた。しかし、伝承の世界でもその流れに従うもの、そうでないもの、現実様々なものが入り乱れ並立するのも事実である。武術的な身体の修練においても「型」が重要視される一方、いわゆる「実戦」も重要であるのは言うまでもない。しかしそれ以外に身体技法習得の方法がない、というわけでもない。「技の創発」というまた違った観点から、身体技法習得の楽しさを知ることもありうると考えられる。そこで我々身体技法研究同志会における試みをここに供覧し、身体技法習得の方法論をともに模索したいと思う。
オルタナティブメディスンはベンチャービジネスの起爆剤となりうるか —その可能性と戦略についての構想—
川人 紫(オルターライフ・ネット)
オルタナティブメディスン(代替医療)とは、西洋医学以外の医療を指す。例えば日本をはじめとするアジア諸国で伝統的に行われている鍼灸やあんま・マッサージ、ヨーロッパ発祥の自然療法であるアロマセラピー(芳香療法)、健康補助食品等がその代表的なものである。米国では、この代替医療を受けている患者数が、西洋医学のそれを上回る程にまでに発展しており、その動きは日本にも確実に波及し始めている。今回は日本や諸外国における現状報告と共に、新しい市場としても魅力的なオルタナティブメディスンをめぐるニュービジネスの可能性について構想を試みたい。
“統合”の構想から見た現代医療の諸相
小池弘人(群馬大学医学部)
近年、医学においては、ゲノム解析、再生医療といった分野が目覚しい発展をとげている。が、一方ではその専門分化も著しく、細分化への批判の声も久しい。こうした中で人間全体としての視点の必要性から“統合”の方向を模索する医学の流れもまた大きくなりつつあるのも現状である。そこで、“統合”というからには、前提として、何かを“分割”したものとして捉えているはずである。現代医療が何をどう“分割”しているのか、この観点から、現代医療のもつ問題点を模索してみたい。
土田杏村の自由大学構想
大村哲・佐藤芳史(特定非営利活動法人NeoALEX社会構想研究院)
大正期に土田杏村が主宰した自由大学構想は、教育の中央集権と権威主義を批判し、その打開策を実践的に示した。社会教育を主とし、学校教育を従としたその運動は、わが国における社会教育の先駆的な実践ともいえる。
本研究は、大正末期から昭和初期にかけて自由大学運動が頓挫していった原因を要約するとともに、杏村の教育観とその構想が21世紀においてどのように生きうるか、その可能性と条件を検討する。宮城大学キャンパスレンジャー隊の構想 〜公立大学における有償ボランティア団体の運営〜
白倉正子(宮城大学)
98年、宮城大学にキャンパスレンジャー隊が発足した。大学の美化活動や案内を行う学生に謝金を支払う、県立大学公認のボランティア活動としてスタートしたが、理想とは程遠い様々な問題との戦いであった。現在、各地でNPO法人が立ち上がり、有償ボランティアの必要性が叫ばれているが、まだ実例は少なく、特に公立大学の学生によるものは少ない。新しい大学教育のモデルとなることを願い、その指導経験と今後の課題をここにまとめる。
構想概念のポルテ
半田智久(PLAOS)
一般に構想は想像におけるイメージを結構してゆく作業と考えられている。だが、歴史を振り返ると、想像のうぬぼれはイメージの結像を決して心像にとどめず、とんでもない怪物を現出させてきた。構想をイメージという代理表象の展開としてみるかぎり、このプロセスは反復されつづけるだろう。いまや構想力のポルテを見定める批判知の形成と発動は人類に共通のメタ構想課題となっている。その課題に応えるべくここではイメージなき構想: 直接構想の可能性に光をあてる。
20世紀、日本の知は何を構想してきたか(1) 〜構想の創生期 ;1900年から45年まで〜
上田勝弘(神戸大学大学院文学研究科)
20世紀の百年間には、多くの構想が提起されました。その百年の構想の系譜をたどることは、20世紀に行われた構想の実情を捉えるために、必要不可欠なことであります。本発表では、20世紀の構想の創生期として、1900年から1945年まで、どのような構想がおこなわれ、これらの構想には、いかなる社会的背景が存在したのか、文献を中心に検討を行います。構想の創生期を検討することで、20世紀の日本における、構想の方向性(ベクトル)を検討することが本発表の目的です。
【 ラウンドテーブル 】
NPO法人制度によるシンクタンク発展の可能性 〜ある政策NPOの活動を通して〜
企画者 福田隆之(早稲田大学教育学部)
発題者 折田裕幸(慶應義塾大学法学部)
村田章吾(慶應義塾大学法学部)
廣飯一彦(慶應義塾大学文学部)
このラウンドテーブルの狙い
特定非営利活動促進法(以下NPO法)の成立によって、従来は財団や社団などの敷居の高い制度を利用しなければ法人化出来なかった非営利活動に大きな転機が訪れた。この制度を利用して、従来は官庁系や大企業系などがその多くを占めていた日本におけるシンクタンクのあり方が、広く市民や議会を巻き込んだ形で新しく発展していく可能性が生まれてきたのではないだろうか?この問題認識を共有した学生中心で立ち上げられた政策NPO(法人格申請中)の実験を通して、その妥当性やあり方について議論する。
戦略的ブランド構想:ブランドは、企業をいかに構想しうるか
企画者 南山宏之(株式会社AXHUM Consulting)
発題者 山田敦郎(グラムコ株式会社)
このラウンドテーブルの狙い
誰にでも、一つや二つ、好きなブランドやすぐに思い浮かべることができるブランドがあると思います。どんな企業も商品も(学校や病院でさえ)ブランドをもっています。私たちは、そのブランドをたよりに商品をえらんだり、就職先を決めたりしています。企業からすれば、いかに「ブランド」を構想し実現するかによって、競争を優位に導き、持続的な発展に導こうとしている、といっても過言ではありません。ブランドとは、ステークホルダー(企業に関わる利益者集団:顧客、従業員、株主、社会など)と企業を結ぶ相互の「約束」。ステークホルダーが期待する価値と企業が提供できる価値を結ぶ「絆」、といえます。本テーブルでは、いかにその「約束」「絆」をマネジメントすることによって、企業の経営や存在を構想できるか、あるいは、その「約束」「絆」という視点から、いかに社会的に意味のある、持続的な発展が可能となる企業活動を構想できるか、を議論することにより、「ブランドとは何か」、「企業とは何か」と同時に、「構想すること」の本質に触れたいと考えています。
討議の端緒として次の3点に関する質問から入りたいと思います。
1) あなたの好きなブランドを一つあげてください。また、あなたが「パワーブランド」であると思うブランドは何ですか。
2) 上記のブランドをあげた理由を教えてください。
3) すぐれたブランドとは、直接的に購買につながる(よく売れる)ものだと思いますか。
構想としての統合医療
企画者 小池弘人(群馬大学医学部)
発題者 山下 仁(筑波技術短期大学附属診療所)
小板橋喜久代(群馬大学医学部)
上田至宏(関西鍼灸短期大学)
川嶋 朗(東京女子医科大学)
山本竜隆(聖マリアンナ医科大学)
このラウンドテーブルの狙い
現状の統合医学及びその関連の医学の流れにおいては、百花繚乱の様相にて、その実態が見えにくくあるのも現実かと思います。しかし、こと医療界の現実におきましては、その分割専門化ではなく、統合の流れの必要性はいうまでもありません。いわゆる代替療法を取り入れることは、患者サイドからの要求は久しいものの、まだ端緒についたところに過ぎません。また、その取り入れにかんしても、問題が山積しているのも現状です。しかし、それでもいわゆる代替療法を、現代医療に統合していこうとする昨今の潮流は、非常に意義のあるものであることには、変わりありません。統合医療、その実現性の是非もさることながら、「統合」というものを「構想」すること、それ自体にも意義があるのではないか、ということを提言したいと思います。これは現状の医学への反省の意味も含め、意義深いことと思います。そこで、このラウンドテーブルでは「統合」を「構想」する先に見える「医療の未来像」がどのようなものかを模索してみたいと思います。一口に統合医学(統合医学会での統合に限らず)といっても、実際、一般の人達にとっては、はやりのEBM(Evidence Based Medicine)の旗手である総合診療といったものも含め、統合だの、総合だのと何がどう違うのか、よく分からないというのが実情だと思います。しかし、統合にしても、総合にしても、学会立ち上げにあたっては、理念というものがあり、そこには何らかの、分かれたものをまとめる、ということにより、良い方向を作り出そうという考えがあるのも事実です。それを、ここでもう一度見直してみたいというのが全体の狙いです。そこで、発題者の先生方には特にそれぞれ、以下の3点についてご提起いただき、一般の方にも分かり易いかたちで現代医療の問題点を討議できたら、と考えております(もちろん問題設定それ自体に問題あり、という立場でも結構でございます)。
1) 何を分断して考えることが問題なのか。(例えば、何々内科等の内科内での専門分化。現代医療と代替医療。医学と看護学。東洋医学と西洋医学、等々。)
2) それをどのようなかたちで統合していこうと考えているか。
3) 各自の“統合”にあたっての利点と巻き起こるであろう問題点は何か。
ケアの視点から新しい社会のあり方を考える
企画者 佐藤 修(株式会社コンセプトワークショップ)
発題者 池川清子(日本赤十字看護大学看護学部)
櫻田周三(慶応義塾大学総合政策学部)
このラウンドテーブルの狙い
今年、コミュニティケア活動支援センターというのを立ち上げました。全国のコミュニティケア関係の市民活動を支援しながら、相互に支援し合える関係を育てていこうという試みです。それに隣接して、インキュベーションハウスという社会的起業家のたまり場をつくりました。ワーカーズコレクティブ方式の会社です。さらにそれと並行して、コモンズ村を育てようと思っています。これは流行のエコマネーにちょっと似ているかもしれません。このセッションでは、この3つの仕組みを題材に、新しい社会のあり方や働きの場を考えていきたいと思います。そしてできれば、大きな福祉ということも考えたいと思っています。論点はつぎのとおりです。
論点1:ケアということを考える
最近失われてきていることのひとつは、「気遣いの文化」ではないか。 近所付き合いのわずらわしさから抜け出そうとするあまり、あるいは「個の自立」憧憬が強すぎたあまり、私たちは大切な人間同士の絆を軽視しすぎてきたのではないだろうか。そんなことを頭に置きながら、改めてケアということの意味を確認したい。
論点2:新しい働き方を考える
働くと言うと、どこかの組織に雇われることと、私たちは考えがちだが、働くということと雇われるということは、全く別のことだ。自分で仕事を創りだしていくこと、それこそが生きることではないか。与えられた仕事から創り出す仕事へと、意識を変えていくことが大切ではないか、そして、その出発点は、もしかしたら「ケア」ということではないか、というようなことを考えたい。
論点3:事々交換を考える
ケアの関係や行為を貨幣に変えることの意味を問い直したい。ケアは一元的な評価基準になじむものなのだろうか。
論点4:みんなが輝くコミュニティを考える
以上の議論が、もしうまく展開すれば、それを踏まえて、みんなが輝くコミュニティとはどんなものなのだろうかを、参加者から一言ずつ私見を述べてもらいたいと思っている。
2002年12月14日(土)9:30-20:00 ・ 15日(日)9:00 -18:30
東京国際フォーラム
【口頭発表】
日本社会への2つの津波に乗って — この機会はいかなる構想の契機か
半田智久(学術NGO・PLAOS)
日本は少子、高齢化という2つの構造変動の中にある。前者は万人への高等教学を実現しつつ、その教育に質的変革を迫る。それは学習者と高等教育の要求の根源的なずれに起因し、従前の機関囲い込み教学の終焉を突きつけている。この変革は今後の社会における新たな知の育成、創出につなげる千載一遇の機会と受けとめられる。変革の機会は急進する高齢化でも同様。長寿への一元評価は見直され、自然な生と死を選択する自由に向けてより開かれた価値転換への言論形成と構想が求められる。本発表ではこの2つの契機を整理し、検討に向けた研究会の設置を提起する。
NPOと行政の協働の条件
渡瀬裕哉(特定NPO政策過程研究機構)
行政機関及び地縁的組織だけでは公共サービスへのニーズに対応することが困難になったことから、その新たな供給者としてのNPOが期待されている。NPOは福祉、環境、産業支援及びバックオフィス部門など様々な分野で既にその専門性・先駆性によって着目される存在になっており今後一層の活躍が望まれる。そのような状況の中で行政とNPOの協働の仕組みについて研究も盛んに行われており、今回はその一事例の発表を行う予定である。
新しい時代の新しい大学 −「榛名山麓みどりの大学」設立構想
太田敬雄(特定NPO国際比較文化研究所)
特定非営利活動法人国際比較文化研究所(他文化理解の研究とその推進を目的として2000年6月設立。会員約200名)では、その活動の一端としてNPOの理念を尊重した民立もしくは衆立とも言うべき大学の設立を目指して活動を始めている。本発表では「榛名山麓みどりの大学」の教育理念と設立構想を、これまでの進捗状況と共に発表し、日本の21世紀の高等教育の在り方に向けての一つの提言としたい。
インタビューとフォト・エッセーから読み解く社会起業家のモチベーション
新谷大輔(三井物産株式会社 戦略研究所)
社会起業家と呼ばれる人々に焦点をあて、彼らがその活動を志したモチベーションとなる情報について、ステレオ・フォト・エッセーと呼ばれる消費者心理分析の調査法を実験的に応用し分析したものである。その方法として、インタビューに加え、彼らに何らかの気持ちが動かされる瞬間を自由にインスタントカメラで撮影して頂き、彼らが日頃、行動基準としていることは何かを彼らが自ら撮影した情景から読み取り、インタビュー結果と照らし合わせ、社会起業家としてのモチベーションとなる情報を分析したものである。
資本主義の成り立ちと新たな経済社会構想
猪岡武蔵(宮城大学)
今や世界は資本主義という経済体制のもと一義化しつつある。世界に存在するあらゆる社会が本来持っていた思想、時間、世界観を世界総資本主義化、グローバリゼーションという大きな波が握りつぶそうとしている。今の日本における“乗り遅れてはいけない“という焦りにも似た状況の中、そもそも資本主義の成り立ちからその発展まで、どういった経緯で今の状況に成りえたか。それから今という時代から時代はどう流れていくのか。現状の経済社会とその成り立ち、そして今新たに始まりつつある新たな社会構想について考えてみた。
regional identityの構想 — 事例研究:花巻の地域構想と宮澤賢治の亡霊
小原智孝(宮城大学大学院)
事例として取り上げる東北の「花巻地方」では、宮澤賢治をモチーフとしたグラフィックが、観光パンフレットや商品・看板などあらゆる場所や機会に拡散して見られ、メタサインともなっている状況がある。注意を払って観察すると、インフラ整備の青写真である花巻市のマスタープランでは「イーハトーブの郷づくり」という賢治の構想した理想郷が掲げられている。これらのように、花巻地方には「宮澤賢治という地域資源」を利用した構造的個性がみられる。本研究はその構造的個性を明らかにし、その個性から構想を見いだしていくことを目的とする。
価値創造を指向する事業と社会システムとの関係性
大村哲(宮城大学大学院)
事業を分類しようとする際、既存の価値体系を利用すること指向する事業と、新しい価値を実践的に提示することを目的とする事業という二極をもった線上に各事業を配置していく方法が考えられる。本研究は後者の極を指向する価値創造的な事業について、それらの構想と実践とが社会システムに与える影響およびその過程について分析する。
脱病院化コミュニティモデルの可能性
荒川創(宮城大学大学院)
今後の日本社会は高齢化が一層進むに伴い、国民医療費の増大という負担が予想される。そこで、医療機関にできる限り依存しなくとも健康的な生活を維持できるようなコミュニティモデルを提案する。それは「薬膳療法」を取り入れた日常生活と地産地消費に基づいた農業のあり方という二つの要素を組み合わせることによって開かれる。本発表ではこのようなコミュニティモデルの可能性を検討するとともに、モデル成立の見込みを検証していく。
大いなる構想におけるペテン師の”魅惑”研究 — 構想実現のためにペテン師の”仕掛け””技”を盗む
若松立行(株式会社スペーストピア)
構想を実現する為にいろいろな制度を調べ、整え、そして官庁、政治家,財界を巡り、大勢の人々と会い時間とエネルギーを使うが理解されず,決定がおくれて、構想自体が没になるケースが多々ある。 経済状況や情報の氾濫、、時代の問題(社会構造の変化、技術の進歩)、プレゼンテーション能力の問題だけでなく、何かが足りないと思うようになった。それが“人々の心”を捉え、感動を呼び、巻き込む、セクシー「ペテン師」「詐欺師」的な仕掛けであるのではないかと思い、ここに、日本構想学会に於いて分科会を設置して、共鳴者を募り、多方面の方々に研究をお願いするしだいです。
景観論争と構想計画 − 京都での展開
片方信也(日本福祉大学)
歴史都市京都では,とくに60年代以降市民は開発の動向をめぐって景観のあり方を論争というかたちで問い続けて来ている・この過程で個々の開発の是非を問う段階から京都全体の都市ビジョンを「構想計画」として提示する計画方法論が登場した・都心の市街地では近隣住民による「まちづくり憲章」などが展開し,コミュニティ形成が重要となっている・この研究発表は,この事例をもとに「構想計画」の意義,方法について述べる。
次世代型ジョイント・ベンチャリングとしての戦略モデル:開発から実践に向けて
加藤誠也(株式会社ダイナアーツ・インターディベロップメント)
史上類のない低金利政策と高い生産性を両輪として一時の隆盛を誇った米国経済は、株主利益に偏向した過剰な株価至上主義や企業会計不正も相まって、急激な失速に転じている。人・モノ・金・情報等経営資源の、一国の経済を超えたボーダレスな流動化が加速化する今日、わが国は米国型旧来システム依存構造を見直し、アジア圏経済の特性・特徴を踏まえた企業活動・事業経営の革新を基軸とした日本のプレゼンス確立が急務であると考える。
本論では、台頭する中国企業・中国資本の国際化展開の一環として推進されつつある日本企業群との提携・パートナーシップ組成の取り組みおよびその戦略構想の具体例の紹介を通して、これからの本邦産業界のアジア展開における課題と可能性を考察する。「事業構想学」への一考察
生嶋素久(宮城大学)
構想力は「知」から生じる。科学史上パラダイム転換をもたらした創造的知はどのように生まれたのか。マイケル・プラニーの「暗黙知」とアインシュタインの「思考実験」の二つを通して、知が構想力に育っていくプロセスを検証する。構想力の次に事業を構想することを考える。事業とは、広義にはprojectを指し、公共的大規模事業やNPOの活動も含まれるが、市場経済の中で生きている我々はbusinessの考察を深めていく。
グレートブックス・セミナーの軌跡と可能性 — ラーニング・ソサイエティの実現に向けて
原田広幸(みずほ信託銀行株式会社)
アメリカの哲学者アドラー博士の開発した教育プログラム「グレートブックス・セミナー」は、日本においても、いくつかの団体による導入が試みられており、成果を上げつつある。この発表では、このセミナーの形式を「自主的な」勉強会のなかに取り入れてきた市民サークル「アゴラ・ソクラティカ」の活動と成果を振り返り、アドラーらが理想とした「学習社会(ラーニング・ソサイエティ)」の実現の可能性を探ってみたい。
北関東統合医療研究会の歩み 〜統合医療という構想の理解へ向けて〜
小池弘人(群馬大学医学部)
「代替医療」という言葉をご存知だろうか。先端医療や医療過誤、福祉医療など医療の世界において話題とされるキーワードの中に、近年、散見されるようになったものの一つである。現代医療の限界がささやかれる中、一種のカウンターカルチュアとして誕生した言葉である。そして、この長所を現代医療の長所と統合し、第3の医学を模索しようというのが「統合医療」である。しかし、既存の大学組織内における、「統合医療」への理解度は極めて低いと言わざるを得ない。そうしたなかで、我々は、研究・教育においてこうした構想を理解してもらうべく、様々な活動を行ってきた。ここに、その活動を報告するとともに、今後の展望について発表したいと思う。
【 ラウンドテーブル 】
自治体の現場から、国と地方のあり方を見直す

小泉首相は、国と地方の財政・税制について、三位一体(地方への税財源移譲、補助金の見直し、地方交付税交付金の見直し)の改革を打ち出した。その実現には、カネ(補助金や交付金)の流れだけを見直すのではなく、カネと仕事がセットで中央から地方に下りている現在の仕組みを変えることが不可欠。複数自治体の有志職員が行った、県の事業の仕分け作業(どこが本来やるべきか?)の分析結果をもとに、改革に必要な視点、具体的アプローチについて議論する。
企画者 冨永朋義(構想日本)
話題提供者 田中康夫(長野県知事)
神奈川県の市役所職員(4市より4名)
細溝清史(財務省主計局)
非営利活動をはぐくむ社会のつくりかた

現在、10万団体、700万人以上が非営利活動にたずわっており、その領域も多岐にわたる。しかし、このような動きを後押しする法制度は整っていない。社会が非営利活動を育て、そしてその活動の広がりが社会を育てることの意義を見出すとともに、芽生えはじめた非営利活動を育てるための仕組みについて議論する。その大きな柱が、100年ぶりの大改正となる「公益法人制度改革」である。現在、内閣府で進められている改革案の検討も含め、制度のあり方を問う。
企画者 長尾亜紀(構想日本)
話題提供者 河北博文(医療法人財団河北総合病院)
丹治幹雄(株式会社メイドインジャパンダイレクト)
原 丈人(DEFTA PARTNERS)
コモンズ社会に向けての新無尽講構想

20世紀は分断の時代でした。近代科学の要素還元主義が社会構造までをも分断してきました。そして、分断された「つながり」をつないできたのが「お金」です。その仕組みが、いまやほころび始めているように思います。21世紀は、「つながり」を回復する時代かもしれません。
昨年、ご報告したコミュニティケア活動が形になりだし、新しい「支え合いの輪」が見えてきました。今回は、支え合いの手段として、お金を活用する、新しい無尽講構想をお話し、コモンズ社会における「支え合い」について考えてみたいと思います。企画者 佐藤修(株式会社コンセプトワークショップ)
話題提供者 小倉美恵子(農的暮らしを考える研究会)
佐藤和美(株式会社SEC[S.Environment Consultant])
西村美和(産業能率大学)
渡辺清(大阪大学大学院)
沖縄地域への航空宇宙産業の誘致に関する構想の実現に向けて

OASIS Plan(沖縄航空宇宙アイランド構想)は、沖縄の地理的・社会的環境を利用した宇宙旅行サービス事業等の航空宇宙産業の誘致による、沖縄・日本・アジア地域の経済発展を目指している。私的見解の下に提唱された本構想の実現には、科学技術・政治・経済等の各分野を融合した学際的研究の実施が求められる。本ラウンドテーブルでは、その第一段階として構想の概要を解説し、予想される課題と解決策を議論する。
企画者 高田尚樹(独立行政法人 産業技術総合研究所)
話題提供者 高橋茂人(株式会社BMネットワーク)
若松立行(株式会社スペーストピア)
アーバンデザイン・ルーラルデザインにおける構想

日本では現在に至るまでさまざまな都市、農村における開発、デザインが進められてきたが、それによって都市、農村における環境が住人にとって本当によりよいものに変化したとは限らない。今後の日本において望ましい都市デザイン、農村デザインを構想していくためにはどのような要素が必要となってくるのか。また、都市と農村における住人のニーズをどのように捉えていく必要があるのか、ということなどについて論じ、参加者の方々と話し合っていきたい。
企画者 荒川創(特定非営利活動法人地域文化創成社爽風白露)
話題提供者 沖塩荘一郎(東京理科大学名誉教授)
大崎元(有限会社建築工房匠屋・「山谷」ふるさとまちづくりの会)
祐川奈津子(宮城大学大学院)
2003年12月6日(土)9:30 - 18:00 ・ 7日(日)9:15 - 20:00
東京国際フォーラム
【ポートフォリオセッション】
コミュニティと共通感覚の関係における可能性
荒川創
今、日本社会の中で「コミュニティビジネス」など「コミュニティ」という言葉が溢れている。しかし、今このコミュニティという言葉があいまいになっている。そこで、本発表ではこのコミュニティという言葉が必要とされたのはなぜなのか、コミュニティがどのような性質のものなのかということを明らかにした上で、コミュニティの可能性を追っていく。その上で、今後のコミュニティ像における構想を個人という観点(特に個人の共通感覚という観点)から論じていく。
新産業を構想する
生嶋素久
Economy, Energy, Environmentの3つのEをキイワードに新しい産業を構想すると、やはり、エコビジネスを考えることとなる。3つのEから派生して地球環境に負荷をかける部分は、二酸化炭素や廃熱つまりEntoropy増大の方向となり、この視点で新産業を考察すると、バイオマス、光触媒、植林ビジネスなど、10年後には30兆円ビジネスといわれる内容を検討する。
現代における道徳のあり方を構想する
姜美愛
今を原点にしてみると「道徳」は「法」とともに政治的に支配しており、その中で法は社会の外的規制で、道徳は個人的な内的規制をするのに利用されている部分が少なくない。四書の『大学』の再解釈によって、そこで語られている道徳と現在存在している道徳のあり方や役割が異なっていることがわかった。人と人との信頼がなくなりつつある今の世の中はものごとに対する価値観が物質的になり、何を先にして何を後にするべきかが混沌としている。世の中を構成している一人一人の人間を尊重し、その一人の人間の中で学ぶ道徳のかたちについて構想する。
「価値創造」を追求するグローバル・マーケティング・マネジメントの新潮流:コーポレート・ベンチャリング(CV)推進における戦略的課題対応モデルを構想する
加藤誠也
長らく続いた閉塞感極まる“底”は脱した感のある経済・企業経営環境だが、新たな時代、新たな成長継続・加速化の原動力としての「価値創造活動」の競争はまさに始まったばかり。グローバルエコノミーにおける競争が当然となった今日、コストカット/コストダウン追求と限られた経営資源による価値内生活動だけでは望むべき競争優位たる価値創造/価値増幅はどんどん困難になっている。本論は、新たな価値創造のエンジンである企業のR&Dに関し、欧米を中心に加速化している、同一組織内部に止まらない経営資源の国際的アライアンス化の動向を鑑み、このコーポレート・ベンチャリング(CV)の取り組みを、これからの本邦企業経営に不可欠な価値創造への一有力な戦略と位置づけ、その組成・推進・加速化において直面する主な課題とその対応への基本モデルを、リソース・エクイティとマーケティング開発の視座から考察・提案する。
悲劇と構想──霸王の生涯から
大村哲
人類はその歴史のながきにわたって戦争をくりかえしてきた。そのなかで、幾人かの支配者は、それまでの社会を激変させ、構想者とよばれるにふさわしい偉業をなしとげた。しかし私たちが彼らの業績を振り返り、それを偉大な構想であると感じるとき、そこには坂口安吾が「救いがないということ、それだけが、唯一の救い」と述したように、構想のかがやきと全き悲しさとが同居している。本研究は、日本と中国における幾人かの霸王を題材として、その生涯と業績を比較検討することにより、構想と悲劇との関係性の一端をあきらかにした。
ビジネスコミュニケーションに関する考察
祐川奈津子
わが国におけるビジネスコミュニケーションは、さまざまに解釈され、利用されている。事業構想学の立場からみるビジネスコミュニケーションとはいかなるものか、P.Fドラッカーの組織論およびRichard.S.ワーマンの理解に関する著書をもとに考察し、実際の現在日本の企業での実態を交えてひとつのビジネスコミュニケーションについての考え方を発表する。
構想を語る著者たちの「構想」の意味
半田智久
公共的に使われる構想ということばに込められる意味をプラグマティックに検討するため、これを書名に用いた新刊書100冊を対象に、著者にこのことばに関して質問紙調査を施し、分析した。その結果、構想ということばが想像やその類義の意味で用いられる傾向は低く、vision-design-conceptの概念三角形で把捉できること、また、構想力に求められる精神特性に情意性が明確に示され、構想ということばに実践的意味を含んだ動態的性質、行為的な意味あいが込められていることが読みとれた。
「構想」から「文化」への解消
遠藤洋史
近視眼的におこなわれた経済的成長への邁進に対する反省から、もはや事業化可能性の高低は構想の質を図る基準ではない。いま「良い」構想を近年あらゆる場で問われている「良識」に結び付けてとらえれば、それは事業の完結によって閉じない価値をもつはずである。本発表ではこのような構想について「実現しその使命を終えたとき社会に受け継がれるべきある種の気風あるいは文化を生むの」と仮定し、事例研究を通してその検証をおこなう。
私設図書館の可能性
清川容子
人は環境によって大きく左右される。寺に行って座禅をするのは、そこが沈思黙考に適した環境であるからだし、受験勉強をする若者が集まる喫茶店も、何かしら受験勉強をするのに適した環境となっているからなのではないか。人が学び、思考するという場面はいろいろ想定できるが、特に読書は孤独のうちになす行為であり、非常に日常的な行為なのである。であるにもかかわらず、場によって、読めたり読めなかったり、頭に入ったり入らなかったりする。人が思考を研ぎ澄ます時に必要な要素を、特に環境という観点から探っていきたい。今回は日本における私設図書館が本を読む環境を提供する上でどのようなことにこだわっているのかを検証する。
共的セクターによる新たな学びの場構想 −グレートブックス・セミナーを素材に−
猪岡武蔵
さまざまな問題が山積している一方で、教育機関に対する信頼は揺らがないもののようにみえる。NeoALEX学術構想研究院の活動において、哲学者アドラー博士の開発した「グレートブックス・セミナー」を起点に、多様で豊かな学びの場を創造するという試みがなされている。共的セクターが提案する新たな学びの形態に対し、その価値と信頼をいかに構築していくか。直接構想という構想のモードをキーワードに、新たな学びの場創造の可能性を探ります。
ベンチャー企業の眼から見た京浜臨海部における産業構造の転換 〜 京浜臨海部ベンチャー企業支援政策提言プロジェクトのご紹介 〜
村田章吾・福田隆之
NPO法人 政策過程研究機構(PPI)では本年の3月から半年間に渡り、京浜臨海部のベンチャー企業支援政策に関する調査・研究、提言活動を行って参りました。本発表ではベンチャー企業へのヒアリングをはじめとする一連の調査活動の成果を基に、戦後日本の高度経済成長を支えた京浜臨海部の産業構造の変化と、同地域の産業振興・ベンチャー企業育成に有益と思われるいくつかの政策案に関してお話をさせて頂きたいと考えております。
>義務教育の求めるもの
小岩聡美
21世紀の混迷する日本の中で、学校という組織はどんな役割を果たし、どんな社会的役割を担っていこうとしているのか。相対化する社会の中で、“義務”とされる教育とはいかなるものか。教師・生徒・社会組織の一部としての視点から見た“教育”というものを、今起きている“学級崩壊”や“不登校”“教育改革”といった現象から考察し、その意義を改めて問う。そして、社会から要請される役割を含めた、“義務教育”の方向性を考察していく。
【クリエイティブ・ワークショップ】
日本構想学会をさらに一層、意義ある場にしていくために
『構想学会を構想する — 自律分散 × 協働』
ハイパーフリーディスカッションによるラディカルブレインストーミングの90分

わたしはこの構想のわたしたちの場(公共時空)に何をしうるか ? ここでつくるのは、「本来の」といいうる公、しかしこの社会においては共といったほうがよいのかもしれないわたしたちの(言説と思考と行為のための)場であろう。その公 - 共を語りあう。
日本構想学会はこれまでの組織原理に対するひとつの挑戦として始まった。それはほんものの随意性(voluntary)とイニシアティヴの集合に支えられた非平衡定常状態にある生命組織である。それゆえにその寿命はやがて潰えるだろう。だが、ここでもうそれを迎えてよいはずはないだろう。クリティカル、クリエイティブ、かつ軽やかなハイパーフリーディスカッションの試み。
【 ラウンドテーブル 】
グレートブックスへの接近からみえてきたビジョン
企画者
半田智久(学術NGO・PLAOS /最高学院構想研究会)
公共領域がもっぱら伝統的な公共団体の行政にゆだねられ、市民の学習機会が阻害されている状況を打開し、ノンガバーメンタルな自由学術の場を育て、最良の学びを果たせる環境づくりを構想している。グレートブックスはそのためのとりわけ重要な基本素材であり、それとの新しい関係のもちかたを実践研究している。
発題者
江藤裕之(長野県看護大学外国語講座)
西洋精神史からみた言語学史、言語哲学の現代的意義、英語学史(特に比較言語学)の知識をベースにした英語教育法開発、一般教養について関心を寄せている。1999年よりかながわ学術研究交流財団が主催する湘南国際村でのグレートブックスセミナーではモデレーターを担当してきている。著書に『グレートブックスとの対話』(かながわ学術研究交流財団,1999共著)などがある。
遠藤洋史(特定NPO・NeoALEX学術構想研究院)
現役大学生として「構想」にかかわる研究に取り組みながら、同時にNPO活動として主に仙台でグレートブックスセミナーを展開してきた。行政とのパートナーシップで同セミナーをおこなう一方、自主運営により、これを事業の核に据えるための試行をつづけている。
小林麻実(アカデミーヒルズ六本木ライブラリー)
経営コンサルタント、マッキンゼーでのナレッジマネジメント実務や、組織論、MBA、学際情報学といった分野での学術研究をおこなったあと、六本木ヒルズの森タワー49、50階に今年4月に開館した会員制ライブラリーで、ディレクターを勤めている。今の東京において、これから古典になってい く可能性のあるコンテンツを所蔵しつつ、人の過去の経験を受け継ぐ新しいシステム、「場」を、リアルとヴァーチャルを融合させつつ構築しようとしている。
鈴木良雄(神奈川県立図書館)
世界の古典・名著であるグレート・ブックスを現代人が読書する場合、社会的にどのような形態が考えられるか。この課題について、アメリカの例を参考とし、日本において公立図書館で読書会が可能であるかを考察してきたなか、公立図書館に内在するさまざまな問題点を提示する。具体的には、公立図書館でグレート・ブックスを、どのようにとらえているのか。公立図書館であるがゆえの読書会運営上の長所と欠点などを解説する。
長島慎治(財団法人かながわ学術研究交流財団)
財団法人かながわ学術研究交流財団は、平成7年から「グレート・ブックス・プロジェクト」の調査・研究を実施し、11年から若手人材育成事業として「湘南国際村グレート・ブックス・セミナー」を開催し、古典の丁寧な読みと討論をとおして、読書法や創造的思考、コミュニケーション能力、表現力などリーダーの資質としての能力を身につける機会を提供してきた。この研究成果とセミナー実践の経験を今後どう展開するかが現在の課題。原田広幸(アゴラソクラティカ)
”生涯「学び」を続けたいと考えるすべての人のためのフォーラム”と銘打って、グレイトブックスセミナーの開催を中心に活動する市民サークル「アゴラ・ソクラティカ」を主宰してきている。その究極の目的は古典的教養、哲学的思考を基本としたコミュニケーションを確立し、われわれ一人ひとりが社会でより善く生きていくための「共通インフラ」を整備すること、参加する意欲のあるすべての人に開かれたセミナーを目指し東京を中心に活動をつづけている。
最高の学びを求めるうえでかなりの確実性をもって語りうるその基盤のひとつは、人類の知の遺産であり、わけても時代の風雪に耐え、いまなお生き続けている古今東西の良書(グレートブックス)でしょう。その意義と価値はあらためて申すまでもなく、すでにその理解と認識のうえに、各所でセミナーやライブラリーが展開されてきています。とはいえ、この動きが日本で目に見えて起こってきてからまだ日は浅く、なによりその価値が求められるはずの教育の現場では、このグレートブックスに耐えうる時間と精神は、いまだこの先の課題として残されています。そこでこのラウンドテーブルでは、グレートブックスのセミナーやライブラリー展開に果敢に取り組んでこられた方々に集まっていただき、それぞれのコンセプトとデザイン、実践をとおして得られた課題や今後のビジョンを紹介していただき、討議をとおして相互理解を進め、あらたな構想にむけての示唆を得つつ、同時にその成果を発信する機会にしたいと思います。
構想者と美意識
企画者
大村 哲(特定NPO・NeoALEX社会構想研究院 /「構想と美」研究会)
発題者
清川容子(宮城大学事業構想学部)
太宰治は第二次世界大戦をまたにかけて作品を残した小説家である。太宰文学の主題は「個」をどう捉えるかということであった。戦時中、太宰は「卑小ながらも社会に伍していくもの」として個を構想した。この構想はニーチェ的な弱者のルサンチマンを体現することが「魂の美」につながるという太宰の美意識がもとになっている。しかし戦後、太宰は新たな社会の中で、個を「滅び行くもの」としてしか構想することができなくなっていた。これもまた太宰の美意識によるものであった。太宰の例も含め、美意識が構想にどう影響しているのか、探っていきたい。
祐川奈津子(宮城大学大学院事業構想学研究科)
20世紀型企業の失敗は、経営における哲学の欠如に原因があるともいわれる。世紀の変わり目のパラダイムシフトのなかで、経営に必要とされる哲学とは美の追求の姿勢ではないかと考えた。21世紀型企業には、その構想において美意識を持つことが必要条件とされるのではなかろうか。本ラウンドテーブルにおいて、参加者各位の美に対する意識を語っていただき、21世紀の個人と社会の構想と美のあり方を模索する。
織田信長は自身の構想を具現化する過程で、きわめて暴虐的な戦術と、民衆に歓迎される政策の双方を実践した。この一見二重人格的な構想の過程は、彼が好んだ幸若舞にうたわれるような、ある種の美意識・無常観によって、統一的に解釈することができる。信長の例にみられるように、すぐれた構想者はその歩みにおいて、ある美意識のもとで判断を下し、また行動している可能性が高い。本ラウンドテーブルは、こうした構想者と美意識との関係について、発題者による事例紹介と、参加者全体でのディスカッションによって検討し、構想において美が果たしている機能をさぐる。
「獲得する平和」の構想
企画者
川本 兼(神奈川県立小田原高等学校)
1948年石川県金沢市生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。著書に、『平和史を築くための理論』(美麻兼のペンネームで著述、自費出版)、『平和のための革命』(美麻兼のペンネームで著述、アイキ出版社)、『国家は戦争をおこなっていいのだろうか』『平和権』『国民主権に耐えられるか』(以上3冊はすじさわ書店)、最新刊に『どんな日本をつくるのか』『どんな世界を構想するのか』(以上2冊は明石書店)日本平和学会会員。
発題者 石井智香(早稲田大学社会科学部)
河田光輔(中央学院大学法学部)
佐藤 修(株式会社コンセプトワークショップ)
水野琢磨(國學院大學史学科)
米澤絵美(明治大学政治経済学部)
佐藤修さんは、コモンズの視点から平和について提言します。河田光輔さんは自らが望む社会を思い描いてみることが必要だと感じており、水野琢磨さんはかつて小林よしのり著『戦争論』から深く感銘を受けたと言っています。また、米澤絵美さんは人間の争いを武力以外で解決する社会の必要を感じており、石井智香さんはすべての人の人権が守られている社会が平和な社会だと考えています。それぞれに自分の視点から自由に話題を提供します。
私たち日本人がこれまで語ってきた平和は、結局は「希望する平和」でしかなかったのではないかと思います。そして、平和憲法も、結局は「希望する平和」を謳ったものでしかなかったのかもしれません。となると、「希望する平和」から「獲得する平和」への転換が必要です。「獲得する平和」の構想——それは、たぶん私たち日本人が創り出していくより仕方ないでしょう。
医療制度改革の本質は何か?
企画者
長尾亜紀(構想日本 政策スタッフ)
独立、非営利の政策シンクタンクである構想日本において、公益法人制度改革、土壌汚染問題、エネルギー戦略を担当。構想日本は、医療制度改革に対し、「医療改革の本質は何か!−医療の質の向上が医療費の抑制をもたらす−」)を提言している。詳細は、http://www.kosonippon.org/prj/c/?no=22 をご参照ください。
発題者
伊藤隼也(医療ジャーナリスト/ 医療情報研究所 代表)
主婦の友社・写真部勤務を経て1982年よりフリーランスカメラマン。1994年、自身の父親を医療事故で亡くした事をきっかけに、医療問題に深い関心を持ち、フォトジャーナリズムという視点から、医療に関する多くの作品を発表している。なかでも、医療分野に関するフォトルポルタージュは、自ら企画提案して、全国の病院や医療現場を精力的に取材。雑誌メディアなどで発表し続けている。同時に市民運動家として、1997年10月「医療事故市民オンブズマン・メディオ」を医療被害者の支援と市民のための医療制度確立を目指して有志と共に設立し、医療改善のための様々な活動にあたる。医療の質の向上という点ではQC(品質管理)が不十分である。医療事故報告の義務化、再発防止策の広報、医師免許の更新など行政として手をつけていない部分はまだまだ多い。さらに、国民の側に医療機関を選ぶ際の基準がないことも問題であり、良貨が悪貨を駆逐することにつながらない。一方、効率性に関しては、医療費の無駄を減らすこととともに、高齢化の進展を考慮し、医療費に国家予算をより回すことも必要であろう。諸先進国に比べて少ないといわれる医療スタッフの増加、逆に多すぎるといわれる医療機関の集約化により医療の安全確保を図るべきであり、かつ患者中心の医療を実現する改革が求められる。河北博文(医療法人財団河北総合病院 理事長)
現兼職として、財団法人日本医療機能評価機構 理事、内閣府総合規制改革会議専門委員、東京都病院協会 会長 等を務める。慶応義塾大学医学部卒業後、シカゴ大学大学院ビジネススクールでMBA取得、慶応義塾大学医学部大学院博士課程修了(病理学)。財団法人日本医療機能評価機構は、病院を始めとする医療機関の機能を学術的な観点から中立的な立場で評価を行い、評価項目の評点が一定水準以上に達している病院に認定証を発行している。出版物に『認定病院評価結果の情報提供』(2003年)がある。当日の議論要旨:「情報の非対称性と市場(レモンの原理)−プロダクト・アウトからパブリック・リレーションズへ−」。今後の医療の課題は、医療の質の向上、 情報(IT)、イコール・フッティング、コストとイクスペンス である。そして、医療は 結果責任 説明責任 不作為の責任 の3つの責任を問われる。これらの全ての基本は医療を利用する人の立場に立った医療を考えることである。医療の主体はそれを利用する人であり、そのために自己責任を伴った選択の自由を最大限可能にすることが必要である。患者さんの意思の尊重を中心に ①医療の質とは何か(検証できる医療) ②医療の情報提供のあり方 ③医療に関わる教育のあり方 ④利用者、提供者双方にとっての公正な環境づくり を議論してみたい。
新藤宗幸(千葉大学法経学部 教授)
中央大学大学院修士課程終了後、東京市政調査会研究員、専修大学法学部助教授、立教大学法学部教授をへて、2002年4月より千葉大学法経学部教授。私はこれまで医療との関連でいうと、ひとつには薬事行政の研究にたずさわり、もうひとつには公衆衛生とりわけ地域保健の研究にかかわってきた。前者については、その一部を拙著『技術官僚』において、また後者については『福祉行政と官僚制』において公表した。電子カルテや臨床研修の必修化を評価するが、日本の医療政策でいささか疎かにされているのは、保健政策との連係ではないか。ライフサイクルを通じた保健をベースとする医療のあり方を考えてみたい。
日本の医療政策は「医療の質の向上と効率性の実現」に向けて動き出しており、その一環として医療のIT化の推進や臨床研修の必修化などを進めている。国民が安心して受診し、納得して選択できる医療には何が必要なのか? 薬害の責任を政府の担当部局に押し付け、医療事故の責任と教訓を医療現場に任せがちな現状を改革するためにはどうすればよいのか? 医療事故、医療現場、医療政策にたずさわる立場から議論する。
>沖縄航空宇宙アイランド構想
企画者
高田尚樹(独立行政法人 産業技術総合研究所・沖縄航空宇宙アイランド構想研究会)
複雑流体現象の解明と数値解析技術の研究に従事する傍ら、個人的な興味から航空宇宙産業に関する情報を収集し、一般の人でも宇宙に行って地球を見れるような有人宇宙飛行の仕事に従事したいという希望を抱き続けてきた。それを契機としてOASIS構想を提案・啓蒙し、本構想の意義や社会に与えるインパクトを評価するため、日本・世界の航空宇宙産業の現状と課題を調査している。
発題者
高橋茂人(BMネットワーク)
「マネジメントゲーム」による経営教育の第一人者として経営コンサルティングを行うとともに、中小企業大学校講師も務めている。長年に渡り教育指導等で訪問してきた沖縄県に幅広い人的ネットワークを構築し、同県の歴史、社会・経済状況に精通しているため、OASIS Planの意義を沖縄に近い見地から検討している。
沖縄航空宇宙アイランド構想は、沖縄の地理的・社会的環境を利用した宇宙旅行サービス事業等の航空宇宙産業の誘致による、沖縄を含むアジア地域の経済発展を目指して提唱された。本構想の実現には、科学技術・政治・経済等の各分野を融合した学際的研究の実施が求められる。本ラウンドテーブルでは、研究会活動の一環として沖縄県で行った講演討論会の内容を報告する他、日本の航空宇宙開発の現状を述べ、本構想の課題を議論する。
2004年12月11日(土)13:30 - 21:00・12日(日)9:15 - 17:45
東京国際フォーラム
【口頭発表】
セブンリベラルアーツ成立前史 : その淵源にみるプラトンの構想
半田智久
リベラルアーツの淵源は自由七科の成立より少なくとも300年は遡り、古代ギリシアで自由人の知と国の守護者への教育を語ったプラトンに求めることができる。彼の教育プログラムは師であるソクラテスの語りを借りつつ、それを転倒させることなく構築、展開された。プラトンはそれを文章にしたためるという行為をつうじて結果的に師を乗り越え、発展させたが、その内容においてはのちの自由七科を構成する数学諸学の強調に踏みとどまる。だが、彼の実際行為からそのビジョンはあきらかに論理にも修辞にも向けられていたことがわかる。それでも、そこは直接ソクラテスとは関係しなかった弟子のアリストテレスに託したのだと思われる。この節制にプラトンにおける強烈な構想の輝きを捉えみる。
日韓共同構想を考える[日韓をつなぐ海底トンネル]
姜美愛
韓国と日本をつなぐ新たなる道、海底トンネルプロジェクトが両国の間であつい視線をあびながら度重なる検討が続けられている。果たして両国にとって海底トンネルはどんな構想的意味をもっているか、想像を絶するような巨額の工事費を費やすこのプロジェクトは韓国と日本にどんなメリットがあるのかを調べ、それに対する波及効果を推測してみた。近くて遠い国という汚名から抜け出し真の心から近い国になれるきっかけとなることを願いつつ発表に臨みたいと思う。
変革の構想〜その 企画構想活動のジレンマ
加藤誠也
長らく低迷する事業環境にあって、多くの 企業が、改革や革新、再構築あるいは再生といったキーワードをその戦略や方針に織り込み、環境変化適合、企業価値増幅に取り組んでいる。優れた経営者であ ればあるほど、その多くが描きたいとする“戦略の焦点”は“変革”にある。しかし、その“変革の仔細”を明らかにしていく意思決定プロセスの実際には、一 見、二律背反する性格のテーマ、あるいは同時併行的実現・対応処方困難な課題への対応が、幾多幾層にも山積するジレンマとして散在している例が非常に多 い。国内空洞化対応とグローバルシフトという問題しかり、継続性の維持と悪循環の切除、あるいは、部分最適化と全体最適化、さらには、日々足元の問題解 決・課題対応として優先されるべき改善と中長期を展望した上で進めていきたいとする改革…等。結果、意思決定成果として出力される戦略は、大別して、変革 の真意の周知・理解を促進し、実効的な協働を推進させる訴求力を具備したアウトプットと、マネジメントの思いとは裏腹に適正な変革訴求に至れないレベルの ものとに分かれてしまう。かといって本論は、多くの先人が長きにわたって積み重ねてきた企業経営における戦略論への論及を意図するものではなく、いくつか の実際の戦略策定、変革構想づくりの過程において“分岐点”となった議論・視座を参考としてクローズアップし、広く社会においてわれわれの多くが関係して いる/していくであろう、“変革という目的を見すえた企画構想活動”への視点再考を行った。
大学生男女の結婚観と結婚・子どもを持つことへの意識との関連
太田麻美
近年、わが国では少子化が進んでいる。2003年の合計特殊出生率は1.29であった。少子化の直接の原因は晩婚化・非婚化だと考えられている。女性の社会進出が進み、無理をしてまで結婚・出産する女性が減少した。社会背景や個人の価値観の変化からくる結婚に対する意識の変化に対して、大学生は現代社会の影響を強く受けていると考える。そこで大学生男女にアンケートを行い、大学生男女の結婚観と結婚・子どもをもつことへの意識の関連を調査した。
商店街の挑戦—「選挙」から「地震被災者支援」まで
高田育昌
今夏の参院選では、早稲田商店会を中心として全国の商店街で「選挙セール」という新しい試みが行われた。「売り上げアップ」と「投票率アップ」を組み合わせるという、この前例のないと試みと併せて、先頃の新潟に県中越地震について被災者を受け入れ(疎開)させるプロジェクトが発足しており、この2つの試みについて報告する。商店街からの新たな「挑戦」から今後のまちづくりの可能性を提示したい。
【 ラウンドテーブル 】
ケアの理論と実践から見えてきた新たなケア教育への構想 —— Care is Everybody’s Business. をめざして

近年、めざましいスピードで開設されてきた看護系大学においては、個別科学としての看護学の確立をめざした研究教育活動のみならず、医療現場で看護の役割とされるケアの実践教育も行われている。そこでは、ケア理論とケア実践のジレンマを乗り越える工夫を通じ、より効果的なケアの教授法のみならず、看護医療を越えたケア教育の新構想が見えてきている。ケアの理論と実践から見た、新たなケア教育の射程と可能性を考えてみたい。
企画発題者
江藤裕之(長野県看護大学外国語講座)
発題者
志村ゆず(長野県看護大学心理学講座)
松崎 緑(長野県看護大学精神看護学講座)
岩崎朗子(長野県看護大学看護教育・管理学講座)
吉田聡子(長野県看護大学大学院博士前期課程)
グレート・ブックス・セミナーの実践活動報告〜おもに、大学・社会人教育の観点から

われわれは、グレート・ブックスつまりいわゆる古今東西の古典良書とよばれるものを「読んで」「考え」「ディスカッションする」という、「グレート・ブックス・セミナー」をそれぞれの現場で実践してきました。このテーブルでは、我々の活動の成果を発表し、「古典良書を、現代社会においてよむこと」の意味、とくに教育的な意味について深く考えて見たいと思います。情報社会、NPO活動や、大学という制度、社会人教育といったテーマに関心のある方、ぜひご参加ください。
企画発題者
原田広幸(アゴラ・ソクラティカ)発題者
木村浩則(熊本大学教育学部)
後藤英司(横浜市立大学医学部)
高等教育インフレーションのなかでの空なる存在構成、そのイニシアティブ — 第2回公開研究会
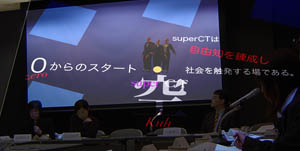
10月のカンファレンスにおける第1回公開研究会では学ぶ当人たちが「学び、考え、行為していく」場を社会文化起業する構想の基本コンセプトと見取り図のひとつを提示しました。本大会ではそれに対して出されたさまざまな意見に対する反応を企画者からコンパクトに示し、あるいはそこからの示唆を反映させた結果を提示します。それらをもとに、このテーブルにおいて新たな意見や企画提案を交わし、さらなる検討をはかりたいと思います。
また、企画者からはとくに教育における決定的な主(aruji)の欠如、その空(kuh)に開かれる価値の構成という観点から、生命的躍動と自由の旗のもとに生成されるイニシアティブへのビジョンが発起されます。また、別の角度から学びの場を事業展開されている方の参加もあります。参加にあたり前回の研究会での参加は前提にしませんので、気軽に加わって意見を聞かせてください。企画発題者 半田智久(PLAOS)
発題者 太田麻美(宮城大学看護学部)
加藤誠也(ダイナアーツインターディペロップメント)
姜 美愛(宮城大学事業構想学部)
佐藤 修(コンセプトワークショップ)
向谷 一(インスティチュート・オブ・ストラテジック・リーダーシップ)
東北イノベーション

東北とは何か。三内丸山遺跡を訪ねると、豊な縄文文化の遺跡が広がっている。東北に住む人々の精神構造がみえてくのです。赤坂憲雄東北芸術工科大学教授は東北学を提唱し、縄文文化を基礎に東北人の精神に迫ろうとしています。日本でも豊な自然が育んだ東北の文化を直視しつつ、東北は日本の地方にすぎないのか、東北は自立できないのか、東北州の可能性はどうなのか。このようなことを考察していると、東北の産業構造のイノベーションに思いはかけていきます。遠藤洋史(宮城大学)は、東北人の精神構造について、生嶋素久(宮城大学)は東北の産業イノベーションについて、考察発表します。参加多数を期待します。
企画発題者 生嶋素久(宮城大学事業構想学部)
発題者
遠藤洋史(宮城大学事業構想学部)
2005年12月10日(土)13:00 - 21:00・11日(日)9:30 - 18:00
東京国際フォーラム
【口頭発表】
リベラルアーツ七科の誕生をたどって — 始まりへの軌跡
半田智久
ギリシア的なものをラテン的なものに結びつけたキケロらは、ギリシア由来の学問の構造をリベラルアーツの語源にあたる名で読み替え、ローマに適った質的変容の契機をつくった。数学諸学は実学と享楽に応用展開し、共和政でもてはやされた修辞弁論が前面に出て、その前提となる文法や補佐役たる論理弁証も重視された。知への愛求も後期ストアのように人生哲学への批判精神に向かった。リベラルアーツは実にラテン的なパックス・コンソルティスへと華開いた。だが、その後、帝国は滑るように凋落。それと塗り替えるようにキリスト教会が知ることの精神を吸引する。一千年を超えて命脈を保つ修道の構想にあったリベラルアーツの取り込みとセブンの呪縛、そのイニシアティブ誕生までのプロセスを押さえる。
産業クラスター地域発展の構想
生嶋素久
産業クラスターは、全国で19計画指定されている。元来、技術集積があるエリアに産官学の英知を結集させようとするものである。東北エリアにも二つの産業クラスターが指定されている。産業クラスターは、新産業を生み出して、産業自体を創出しようというものであり、21世紀の日本の産業活性化をめざすこととなる。アメリカの産業クラスターとの比較を交えつつ、21世紀の日本の姿、少子高齢化、新旧産業の交代、女性の社会参画など、変貌する社会を見据え、新産業の必要性を構想したいと考えている。
グリーンツーリズムの普及における情報提供のあり方を考える
姜 美愛
ヨーロッパが発祥地であるグリーンツーリズムは30年以上の歴史があり、農山漁村でホームステイなどを通じて過ごす長期休暇として知られている。日本でも持続可能な観光資源を基盤に新たな農山漁村の産業として構築していくことを目指し、10年以上にわたり定着に取り組んでいる。だが、いまだ一般にはその存在や意義が十分認識されていない様子である。そこで一般市民を対象にした質問紙調査を行い、旅行代理店や旅行情報誌、インターネット等の情報媒体がグリーンツーリズムに関する情報伝達に果たしている程度をつかみ、問題を確認した。本報告ではその結果とそれをもとに、グリーンツーリズムの認知度を上げるための情報媒体活用の構想について提起する。
異文化圏との構想の交換〜中国・広東省・広州市におけるプロジェクト開発の実践事例を通して
加藤誠也
経済発展著しい中国沿岸部及び南中国エリアでもとりわけ群を抜いたGDP成長を記す広東省の省都・広州市。2005年現在における社会文化的生活の成熟度は日本の1967年の水準に匹敵するとする研究があるように、著しい経済成長とは裏腹に未だ発展途上にある中国のサービス経済の現状に相対して、近年世界水準のQOLに資する商業サービスを提供することを目的とする現地資本によるプロジェクトが多数進展している。本発表では同国におけるいくつかのプロジェクトの構想策定段階からのプロデュースワークに関与している実務経験を通して学んだ異文化圏におけるプロジェクト構想策定プロセス上の問題をクローズアップし、課題対応の方向性を考えてみたい。
【 ラウンドテーブル 】
ジョン・デューイ『学校と社会』を読む

20世紀アメリカの哲学者デューイによる教育理論は、アメリカ本国にとどまらず、日本においても戦後「教育改革」において採用された。彼の主張は伝統的な管理教育への批判として読むことも出来るが、実は彼の哲学的な立場(そしてアメリカ独特のプラグマティズムの思想)とも深く結びついている。【それは二元論に対する反対である。すなわち、彼においては、理論と実践の分離は二つの存在論的領域(普遍的イデアの世界と具体的個物の世界)の分離に対応し、哲学的にも、そして教育においても、この二元論を克服する道を探った。】良い意味でも悪い意味でも、このデューイの思想は、我々の現代社会の教育のモデルのひとつとなっている。教育学の古典でもある同書を読み、現代社会における教育のあり方を構想してみたい。【参加者は、岩波文庫『学校と社会』青652-2(¥410)をご用意ください。】
話題提供者 原田広幸(日本構想学会正会員)
大光寺耕平
ジャーナリズムを通して知る、デザインの力
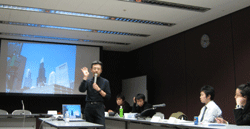
デザインジャーナリストという肩書で仕事をしてきて、いかにこの職業が誤解されているかということを強く感じている。その立ち位置の曖昧さに悩み、41歳で一年発起、ジャーナリズムで全米トップクラスのミズーリ大学コロンビア校に留学。 わずか半年しか在籍しなかったジャーナリズムコースの大学院で、驚くべく事実に出会った。デザインジャーナリズムとは、「デザイナーを映し出す鏡」である。その鏡にニッポンのデザイナーはどのように映っているか。デザインジャーナリズムの意味とその課題を語ることによって、「ニッポンデザインの真の力」を検証する。
話題提供ゲスト 山本雅也 (デザインジャーナリスト)
1961年生まれ。写植システムメーカー・写研・宣伝部の仕事を通してグラフィックデザイナーにインタビューし、デザインの面白さに触れる。そのため、デザイン書籍専門出版社・六耀社の編集部へ転職。その後、月刊デザイン誌『FP』(学習研究社)副編集長を経て、93年よりフリーランス。2002年、日本におけるジャーナリストとしての立ち位置に悩み、41歳でアメリカ・ミズーリ大学コロンビア校ジャーナリズムコースに留学。帰国後は、「デザインジャーナリストはデザインそのものを語るのではなく、デザインを通して社会現象を語るべき」という独自の信念で活動を再開、執筆のみならず、各種講演やデザインイベント司会、「Design Channel」 (テレビ東京)コメンテーター、桑沢デザイン塾(桑沢デザイン研究所同窓会)講師など、活動の範囲を拡げている。近著に、『"インハウスデザイナー"は蔑称か』(ラトルズ)。
ブランディング研究とデザイン教育における構想課題

ブランディングの研究は近年ますます進んでいるが、わが国においてその成果はどのようにあらわれているだろうか。欧州の事例をみるとブランディングにおける構想の課題があらわにみえてくるようである。この状況の背後を探ると、こんにちの教養にみるデザインの価値認識にかかわるテーマが浮き上がってくる。現実の事業展開とその基盤となる教育ないし社会・文化環境の関係を結びつけ考える場の形成を試みる。
話題提供者 南山宏之(AXHUM Consulting)
リポジショニングとブランディング: 最近の欧州における事例から —英国図書館・ユニリーバ・オランダ軍
中西元男(PAOS・早稲田大学)
現代人の必須教養 : 読み・書き・算盤、そしてデザインヒポクラテスの誓い

『ヒポクラテスの誓い』は英文にすればわずか400単語に満たない宣誓である。だが、そこに記された意味は重いとみえて、成立から数千年の時を隔てた今もとりわけ西洋近代医療の教育課程では必ずといってよいほど、とりあげられる。また合衆国の医学校ではほとんどが卒業時の宣誓文に用いているともいう。その重さは何故か、またこれが生命倫理や医療倫理の観点から、少なからず批判的思考を養う格好の素材としてとりあげられる所以は何か、をあらためて探り、そのうえで検討を加えてみたい。
話題提供者 後藤英司(横浜市立大学)・雨宮愛理(横浜市立大学)・稲垣萌美(横浜市立大学)・北井勇也(横浜市立大学)・中尾 聡(横浜市立大学)・鈴木景子(横浜市立大学)・竹蓋清高(横浜市立大学)
ゲストコメンテーター 河原直人(早稲田大学)
jssi: この5年間の成果と新たなフェイズへの構想 わたしたちが向かうところ

日本構想学会は21世紀の幕開けと共に活動を開始し、今年度で早くも5年目を迎えた。これまで「構想」という概念を核にしてそこに行き交うさまざまな営みを幅広く研究し、促進し、学びあうことを主たる目的として活動してきた。当学会はそれ自身がひとつの構想としての実験精神を宿していたから、その足取りそのものが研究対象であるともいえる。5年という区切りの時点において客観的な成果をみるに、ひとつのフェイズが終わったことを示しているようにみえる。ここまでの経験を活かして、次の段階へのメタモルフォーゼの姿や方向性を具体的に検討したい。
話題提供者 半田智久(日本構想学会事務局)
2006年12月9日(土)9:00 - 21:00
東京国際フォーラム
【口頭発表】
「構想」を書名にした新刊書の発行状況
半田智久
現代の日本では「構想」を語る言説が社会のあらゆる場面で好んでおこなわれているように見受けられる。その印象の裏付けを求めて2001年から5年間にわたり「構想」ということばを書名に使った新刊書籍の発行状況を調査した。その結果、同期間中に発行された書籍点数は196点、60ヶ月にわたって1度の例外もなく、毎月「構想」ということばを書名に掲げた新刊が出版されつづけていたことがわかった。報告では版元やジャンルの偏りなどに関する内容分析の結果をあきらかにする。
看護師としての成長
小岩聡美
"看護"〜"医療者対患者"という視点ではなく、"共に生活する人として"という視点を持ちつつも、"医療を提供する"という関わり、とはどういうものなのだろうか。看護学生としての実習体験を通じ、今改めて医療における人と人との関係を再考する。
構想の具現化を阻むもの〜中国・広東省・広州市におけるプロジェクト実践プロセス事例から学ぶプロジェクトマネジメント推進への一考察
加藤誠也
昨年小論は、異文化圏における構想の交換そして策定の取り組み、具体的には、中国・広東省の省都・広州市において小職(弊社)がプロデュース業務を受託しているプロジェクト「珠江新城・凱旋新世界Central Park View L8区複合ショッピングモール開発(開発主:新世界中国地産業広州)」を事例として取り上げ、その構想策定プロセスにおける諸課題への考察を行った。同プロジェクトは当初本年12月の開業を目指したものであったが、本年8月段階において、およそ半年の開業予定繰り延べを余儀なくされるものとなった。本論は、昨年の「策定」フェーズを経て、「具現化」フェーズに進行した「構想」をあらためて事例として取り上げ、一構想の実現・具現化プロセスにおける困難、とりわけ関与する複数の主体・組織のコンカレントワークの推進において小職が直面している(してきた)課題と課題対応への取り組みを題材として、異文化圏にまたがる構想具現化への営み、そのプロジェクトマネジメントにかかわる諸問題と問題解決へのクリティカルパスを考察する。
プロジェクト発生の原理・誘発性の分析および新規創成デザインのためのフレームワーク
長 香奈恵
プロジェクトは人間の社会的行動の1つと言える。その原理・誘発性を捉える為には環境、風土などの人間社会を取り巻く外部要因に加え、心理、価値観、文化などの内部要因も起因する。それらの状況をフレームワークにすることで、プロジェクトという行動の運動性・影響分析および新規創成のためのデザインワークのスタイリングへ応用したい。本発表ではそのフレームワークのアウトライン、基礎モデルの仮説を示したい。
【 ラウンドテーブル 】
ケア教育への新たなコラボレーション ―― ケアの時代を生きるために

ホリスティックなケアを実践するために、看護職者は患者を一人の人間として看るという姿勢を大切にしている。それゆえ、看護教育の場では、さまざまな視点から「人間とは何か」を考える機会が重視され、看護に必要な基礎知識と技術を教えると同時に、哲学、倫理学、文学などの人文学系の科目を必修として学生に課している。このような看護と人文学系の科目の接点となっているのが「ケア」という概念であろう。本ラウンドテーブルでは、看護をめぐってのさまざまな「ケア」を教えるという視点から、一看護系大学における看護系教員と非看護系教員とのコラボレーションについて報告し、看護系大学における一般教養教育のあり方を考え、「ケア」概念を軸とした対話型授業プログラムの構想を提示する。
企画者 江藤裕之(長野県看護大学 外国語講座)
水嵜知子(長野県看護大学 生活援助学講座):看護の基礎教育の立場から 「ケア」の理論< ケアの心を教えること
松崎緑(長野県看護大学 精神看護学講座):看護の実習現場から 「ケア」の実践 察すること 解釈すること
江藤裕之(長野県看護大学 外国語講座):一般教育の立場から グレート・アイディアとしてのケア 人間理解のための「ケア」概念を学ぶ対話型授業プログラム
DECOMAS 21.5公開研究会 DECOMASの導入方法
およそ35年前、経営戦略としてのデザイン統合という主題のもとにDECOMAS(Design Coordination as A Management Strategy)は、その理論と実践の体系を確立する創意と独自性をもって世に提起された。この書はその後、我が国の幾多のCorporate Identity計画において名実ともに指南役となり、多くの実践家の糧として計り知れない影響を及ぼした。いまや、CIは汎CIとして企業活動のみならず教育機関や自治体などを含む広範な非営利事業においても、その営みにおける不可欠のプロセスとなり、その一環として位置づけられたブランディングに対する認識と理解もコモンセンスといいうるところにまで高まるところとなった。
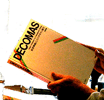
わたしたちはその書の著者を含め世代や領域を超えた場において、時の検証をもってDECOMASに見いだされる普遍を抽出しながら、この先に向けての理論を描きつつ、新たなる指針を見いだそうと1年間のスケジュールで研究活動をおこなっている。このラウンドテーブルではその第7回目にあたる定例の研究会をメンバー以外の参加者を含めて公開形式でおこなう。この回の内容は同書第3章の「DECOMASの導入方法」のなかの社内における予備的検討/ 経営理念と経営方針の明確化/ 現在のCIの評価と問題点の摘出 / DECOMAS導入の勧告、の範囲を典拠に、韓国におけるDECOMASの現況概観を加える予定で、報告と同時に参加者の自由なディスカッションを企図しています。
企画者 半田智久(日本構想学会事務局)
報告主担当 姜 美愛(株式会社YKC)
DECOMAS 21.5研究会メンバー
猪岡武蔵(株式会社アイセル)
猪熊 玲(PAOS))
荻原実紀(PAOS))
金子英之 (i2))
小出葉子(ジュエリーデザイナー))
中西元男(PAOS))
原田広幸(桐生短期大学))
檜垣万里子 (慶応義塾大学))
牧口早希子(筑波大学))
松村孝弘)
南山宏之(AXHUM Consulting)
「白い航跡」をよんで

『白い航跡』(eg.,講談社文庫 1994)は本年79歳で逝去した文人吉村昭の1991年の作品で、薩摩藩の軍医から身を起こし、1881年に東京慈恵会医科大学の前身、成医会講習所を創立した高木兼寛(1849-1920)の伝記。
高木といえば、陸軍軍医でもあった森鴎外と脚気の原因をめぐって論争した話がよく知られている。脚気は明治のはじめまでは多くの軍人を悩ませた死に至る病であったが、高木はその原因を日々の食事に求め、感染症説をとる森鴎外らと対立した。その背後には医に対する独自の視座があった。明治期から看護師養成にも力を尽くし、全人的医療の立場に立って「病気を診ずして病人を診よ」の精神を導いた。日本の医療史における代表的な構想者の一人といえよう。企画者 後藤英司(横浜市立大学医学部)
報告 大谷菜穂子(横浜市立大学医学部)
面谷透君(横浜市立大学医学部)
西山邦幸(横浜市立大学医学部)
ポスト産業主義の社会とは、どんな社会か
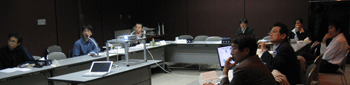
日本型経営社会は、アメリカ型経営社会へと移行を迫られている。企業は誰のものか。株主のものである。日本型の従業員中心の考え方が否定されかかっている。しかし、ポスト産業主義を提唱する岩井克人東大教授によれば、情報社会が進行する現在、商品の価値を決めるのは、コストではなく、商品の差や違いということになる。つまり、商品の差異を決定するのは、従業員、社員の相違感覚、知恵ということとなる。こう考えていくと、産業社会は、資本ではなくなってくる。ポスト産業主義社会は、現在の資本主義社会とはちがってくるのである。
企画・報告者 生嶋素久(宮城大学)
2007年12月15日(土)9:30 - 19:10
東京国際フォーラム
【口頭発表】
構想力におけるビジョンの特性
半田智久
人は一般に構想力にビジョンとしての性質を読んだり、託したりしている。むろん構想は複合概念として理解される精神過程であろうから、その力を単純に別の概念で置き換えて理解できるとはいえないだろう。だが、構想力の理解にとってそれがもつビジョンとしての固有特性をとらえることは不可欠のアプローチといえそうである。本報告ではその試みとしておこなった分析的考察の一端を紹介する。
Web2.0時代における信頼の意義と新たなプロジェクトの構想
猪岡武蔵
Web2.0という言葉はさまざまな言説の中で多様な解釈がなされているが、それが使用されている場面ではインターネットを中心とした情報通信の在り様が新たな局面を迎えているという認識では一致を見ているように思われる。そのようななかで、個人が表現者として発信する動機付けとなる共有の認識として"信頼"という概念の重要性が認識されつつある。それではWeb2.0時代における"信頼"の意義とは何か。いくつかの信頼の先行研究と事例から迫ってみたい。
プロジェクトの価値的研究 -プロジェクトと価値形成の関係分析-
長 香奈恵
プロジェクトへの考察は諸面のアプローチが考えられる。そうした中で、プロジェクトという現象或は出来事をどのように眼差すことができるだろうか。その時、現象或は出来事一般の基本原則と照らしあわせることで、その特性がみえてくると考える。ここでは、その価値的特性を掴むために、西田幾多郎氏の『善の研究』のうち「第三編 第四章 価値的研究」を参照し、プロジェクトの特性と価値的形成を分析する上での課題を提起したい。
【 ラウンドテーブル 】
「戦略」研究、この先1年の構想

「戦略」ということばは穏やかではありませんが、実に幅広い領域、場面で、しかも好んで使われているようにみえます。これは人類の好戦性をあらわしているのでしょうか。ともかくもその結果、この社会に生きているかぎり、顕在的にも潜在的にも、好むと好まざるとにかかわらず、わたしたちはいくつもの戦略にかかわることになります。ただ、その語用の多様さからすれば、意味の幅も相当に広がっていることでしょう。しかるに、わたしたちの一般的な認識は果たしてその生きたことばの生態に追いついているでしょうか。この問いかけに対して答えが曖昧であるとすれば、わたしたちは戦略の足下でその履き違いをして、およそ戦略とはほど遠いおこないをしながら、ただ名ばかりの戦略にかかわり、結果的に戦略を貶めているおそれもありそうです。この点で戦略は構想と同様の問題性を抱えた概念といえます。本研究会では双方の概念の共通性にも照らしながら、1年間のスケジュールで多角的な視座で現代における「戦略」とは何であるのか、を探り、その実際の姿と可能性に迫り、幾分かでもはっきりさせる試みに挑む所存で設置されました。このラウンドテーブルはその第一回の研究会であり、会全体の方向性や目的、予定、目論見を確認、共有しつつディスカッションを進めました。
企画者 日本構想学会「戦略」研究会
話題提供者
猪岡武蔵(株式会社アイセル)
大橋一章(早稲田大学)
金子英之(i2デザインアソシエーツ)
河野龍太(インサイトリンク・アンド・アソシエーツ株式会社)
佐藤修(株式会社コンセプトワークショップ)
智片通博(オールニッポンヘリコプター株式会社)
長香奈恵(日本構想学会正会員)
鳥羽瀬孝臣(J-POWER/電源開発株式会社)
中西元男(中西元男事務所・PAOS)
原田広幸(日本構想学会正会員)
半田智久(静岡大学)
松原智美(早稲田大学)
個人の空間から、共同する空間へ ?プロジェクト研究会の推移と展望

プロジェクト研究会を2007年2月にスタートした。研究会を語る上でかかせない象徴的なイメージとなったのは、Projectの原義だった。それは「前へ投げる」ということ。そのイメージから何かを汲み取ってくれた方々が集まり、研究会として成立することになった。
実験 研究会はさだかならぬ先行きをもった船として出航することになった。なぜこの船の行き先がさだかならぬものであったかというと、行き先には何か既存のものとは違う変化が訪れるのではないかという期待とともに、具体的にどこに行くかわからぬ不安とが共存する状態であったためだった。その前提のもと、研究会はラウンドテーブルという実験を行った。それは、個人的な思考空間の中で捉えていた「プロジェクト」というイメージを共同空間の中で捉え直してみる試みであった。それは、漠とした、混沌としたイメージをテーマとして、はじめてEメールという仕組を通して、ネットワークで語ってみるような、先行きのわからない試みであった。
ラウンドテーブルへの期待こうした思考の変化があるなかで、私たちはどういった変化の先へたどり着くことができるのだろうか。今回のラウンドテーブルのディレクションには「変化の方向性」という文脈の中でプロジェクト研究会を再定義してもらうような実験ないしは試みを期待している
企画者 猪岡武蔵(日本構想学会正会員)
話題提供者
長香奈恵(日本構想学会正会員)
半田智久(日本構想学会事務局)
2008年12月6日(土)9:30 - 20:00
東京国際フォーラム
【ポートフォリオ発表】
日本におけるプロジェクト概念受容の一考察
猪岡武蔵
現在、「プロジェクト」という語を用いた活動が社会の様々な局面で使われている。だが、「プロジェクト」という言葉について改めて考えると、日本語に相当する言葉が存在しない事に気づく。これは、この言葉の語義(pro+ject/前へ+投げる)から発した概念は、日本語および日本文化を背景にした場合、咀嚼が難しいからではないだろうか。本研究では、日本におけるプロジェクトの理解の有り様を神話表象、文学表現、日本語の特性から探ることを目的とする。
戦略概念の一般化過程を確認する
半田智久
ここ半世紀に進行した経営・ビジネス分野での戦略という用語使用の一般化過程を、当該分野で刊行された書籍書名、創刊雑誌名、一雑誌の掲載論文名の3指標で、その年間頻度推移をとらえることで検証した。その結果、同分野での戦略という用語の導入は60年代前半になされたが、使用傾向の上昇は80年代頃から徐々に認められ、世紀の変り目を契機にして短期間のうちに一般化が進んだ状況があきらかになった。出自を軍事用語とした戦略は当初はその意味合いが経営分野で有効に転用できたかもしれない。だが、今やほとんど雰囲気語として深い意味をもたずに使われるほど汎化し、術語としては特定の意味生成機能が摩耗し、非戦力化したといえるかもしれない。
シュルレアリストのイメージを巡る戦略とパウル・クレー
宮下誠
美術雑誌「カイエ・ダール」誌、1926年、第8号、筆者はロベール・デスノスによるシュルレアリスム絵画についての論考を発表する。ここで重要なのは、この記事にクレーの図版が、それもよりによってテクスト冒頭に掲載されており、これを通して、クレー作品を見るものにシュルレアリストの戦略「シュルレアリスムの先駆者」としてクレーを祭り上げ、シュルレアリスムの故郷が硬直したフランスではなくドイツであると意識させるいう屈折して手の込んだ戦略が透けて見えるのだ。読者はこの二つの「表象」"SURR?ALISME"とクレー作品の図版が併置されたとき、必然的に「クレー=シュルレアリスムの画家」という固定的イメイジを持つだろう。「カイエ・ダール」誌は、パリはもとより、ドイツの、パリの動きに敏感な批評家、ギャラリスト、公衆らによっても知られていたに違いない。とすれば、この、方向性を強く持った固定的イメージの形成性は大きな拡がりを持つものであったと言えるであろう。
「開発」と「保護」を共存させる戦略的対処 -順応的管理(adaptive management)の実践例-
鳥羽瀬孝臣
自然現象は不確実である。それは、自然現象が確率論的に起きること、自然のことをすべて知っているわけではないこと、自然現象を観察する能力に限界があることに起因する。自然改変を伴う開発行為において、生態系を保全しながら開発を進める場合に、順応的管理(adaptive management)の概念を導入して、P(Plan/仮説)-D(Do/実施)-C(Check/検証)-A(Action/見直し)サイクルの中で戦略的に対処する必要があり、その実践例を紹介する。
東寺講堂諸像と空海の戦略
松原智美
京都東寺の講堂に安置されている21体の彫像は、空海の構想にもとづいて制作された立体曼荼羅である。この講堂諸像については、いかなる教義的意義をもつ曼荼羅であるかが議論されてきたが、そこに特定の教義的意義はみいだし難いことを指摘したうえで、入唐求法から帰朝した後の空海(とくに最晩年)の事績が何を目的としたものであったかを考察することによって、講堂諸像の制作を、真言密教の地位向上をめざす空海の戦略の一環として位置づける。
企業経営における戦略についての考察
河野龍太
本来は軍事的概念であった戦略が企業経営のコンセプトとしてビジネスの分野に持ち込まれて以来50年近く経ちました。今日戦略という概念はビジネスではきわめて広く普及しています。企業経営における戦略とは何かについてこれまで議論されてきたことをふり返った上で、戦略がかかえる今日の問題と今後の在り方や方向性について考察をいたします。
戦略(strategy)の原義 - その進化・多用に見られる脈絡(context)から考察される示唆的方向性
加藤誠也
「戦略は知識以上であり、実際生活への応用であり、流動的な状況に従う創造的な思考の発展であり、困難な状況における行為の芸術である。(モルトケ)」 「戦略とは一般的には長期的視野、複合思考で特定の目標を達成するために力や資源を総合的に運用する技術・科学である。(栗栖 弘臣)」 戦略の定義は、時代・地域・分野によってその意味は異なっている。‘戦略’というその字自体が示すように軍事的な用語としての使用が最初であったであろうことは誰しもが容易に推察できるものである。しかし、今日多用されている軍事以外の多くの分野では、もともとの軍事における概念が当該分野に応用されてはいるものの、使用される分野、分野において、独自な定義をもって活用されている、あるいは拡散しているように思われる。日本では戦後に企業の経営戦略のように使用されたり、また経済戦略や外交戦略のように政策と同義語として使用されることも多く、また戦略的という形容詞が多用されることも重なって、「戦略(strategy)」という言葉自体、今日では、政治・経済、企業経営においてはもちろん、スポーツや個人のライフデザインに至るあらゆる分野で使われるものとなっている。本研究は、こうした戦略/strategyの原義からのその一般化、変意、進化を、戦略/strategyが定義する対象ならびにその言葉が意味する脈絡(context)のliberalizationととらえ、そのliberalizationがもたらしてきた/初発・誘発してきた方向を考察することによって、戦いに勝つ/勝つために…という文脈を超えたわれわれの営みにおける示唆を抽出し、その方向を読み解くことに主眼を置くものとした。
【 ラウンドテーブル 】
「戦略」研究会一年間の活動を終えて

この1年間の各リサーチメンバーの課題についてのファイナルコメント(感想)とディスカッションメンバーを含めた最終の成果を踏まえた総合的な討論をおこないます。このラウンドテーブルは研究会メンバー以外の方も参加します。
企画者 日本構想学会「戦略」研究会
加藤誠也(株式会社ダイナアーツ・インターディベロップメント)
河野龍太(インサイトリンク・アンド・アソシエーツ株式会社)
半田智久(静岡大学)
松原智美(早稲田大学)
宮下誠(國學院大学)
猪岡武蔵(株式会社アイセル)
佐伯真一(株式会社dmp)
佐藤修(株式会社コンセプトワークショップ)
長香奈恵(日本構想学会正会員)
鳥羽瀬孝臣(J-POWER/電源開発株式会社)
姜美愛(日本構想学会正会員)
新次元の経営を構想しデザインしていく

経営とは、ことにあたってあれこれと奔走するという営みにおいて、筋道をしっかりつけたり、経=スートラ(戒律)を設けるようなことを意味しているとも読み取れるコンセプトです。企業経営や事業経営、あるいは学問経営にせよ人生の経営にせよ、少しばかり縮こまった観のある昨今の社会のなかで、先々に新たな希望を見とおすことのできる新経営の構想やデザインについてご一緒に考えませんか。このラウンドテーブルではこのテーマでの研究会の可能性について参加者のみなさんから自由なご意見をちょうだいし、論じあっていきたいと思います。
企画者 半田智久(静岡大学)
プロジェクトという行為の原点と展望をめぐって
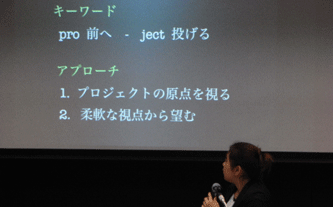
プロジェクト研究会では、昨年度より「プロジェクトとは何か」という原点に視座を置きその行為の内実と可能性について改めて検討し、新たな視野と展望を開拓しています。現在、個人研究活動を通じて「前へ投げる」(pro-ject)という言葉の原義へ柔軟な見地から題材をとらえ考察をおこない交流しています。このラウンドテーブルでは、研究会コアメンバーからの三つの話題をきっかけに、ご参加の皆様の自由な視点からご質問をちょうだいして、研究課題を深めていきたく存じます。プロジェクトという行為の原点と展望をめぐって、双発的に創発的対話を重ねる進行をとれれば幸いです。皆様のご参加を楽しみにお待ちしております。
企画者 長香奈恵(日本構想学会正会員)
話題提供者
猪岡武蔵(日本構想学会正会員)
加藤誠也(日本構想学会正会員/ダイナアーツ・インターディベロップメント)
半田智久(日本構想学会事務局)
2009年12月5日(土)9:30 - 19:30
東京国際フォーラム
【口頭発表】
知能環境論の再構築
半田智久(お茶の水女子大学)
1996年、『知能環境論』を上梓して人間の知的機能に関する環境論的視点を提起した。それ以来、この約15年の社会動静はインターネットと携帯無線通信の普及によって外在する知のありようが遍在化し、その生態は質的に変容しつつある。この外在知のエコロジー進化を左右するのは内在する知の働きかけにほかならないと思われるが、この決定的な局面に求められている条件はなにか、という観点から知能環境論の再構築を構想する。
大衆メディアの未来と絵解き ―人間的なるものの再考―
西岡亜紀(お茶の水女子大学)
web革命以降、今や個人が、好きな場所から文化を発信できる時代になった。20世紀の主要な発信源であったテレビ、映画、出版ですら、過去のものという観がある。そうした時代だからこそ、文化を発信することの人間的な要素とは何かということを論じたい。議論の視座として、「絵解き」という前近代における一つの情報媒体について、映像も交えて紹介する。「絵解き」とは、絵を見ながら節のついた語りを行う芸能であるが、17~20世紀前半の東西において、民衆への文化の伝承や教育に重要な役割を果たしていた。またこれは幻燈や出版の発生とも無関係ではない。ゆえに、過去から現在、そして未来の大衆メディアのあり方を考える鍵となるだろう。
リスク・コミュニケーション
鳥羽瀬孝臣(正会員)
安心は安全と信頼の上に成り立つ。専門家(技術者)はその専門能力を使って安全を提供できる。専門家が公衆から信頼されるためには、専門的能力、倫理的行動、公衆との価値観共有の3つが必要である。そして、そのような専門家の姿を公衆に正しく知ってもらうことが、リスク・コミュニケーションの要である。
【 ラウンドテーブル 】
Topical thinkingの構想

「今はクリティカばかりがもてはやされ、トピカは先におかれるどころか、すっかり見過ごされている」18世紀のはじめ、デカルトの方法的懐疑で着火した科学的思考法が学問の世界で勢いをつけはじめ、人びとが理性に目覚めだした頃、芸文を学ぶ青年たちに学問の方法を説いたGヴィーコが鳴らした警鐘であった。その残響は3世紀が過ぎた今もわたしたちの足下から身体に伝わってくる。クリティカルシンキングは確かに思考の仕方のひとつとしてたいせつなものにちがいない。だが、それが強調されすぎ、習慣化していつも先に立つようになることはせっかくの知性を蒼白いままに痩せさせ、やがては惜しくも萎えさせてしまうことになるかもしれない。思考のバランスをとるためにも、またクリティカルシンキングをできるだけ的確になすためにも、トピカル・シンキングのありようや方法が明示化され、実践の機会形成が構想されてしかるべきように思われる。このラウンドではそうした観点からトピカル・シンキングをどのように考えたらよいか、そのトピカをご一緒に探る時間をもちたく思います。
企画発題者 半田智久(お茶の水女子大学)
『高瀬舟』を読んで

森鴎外の『高瀬舟』は短編ながら現代につうじる重要な課題をテーマにしている。そのひとつである安楽死の問題はもちろん、この物語から滲み出るいくつかの論点や構想を参加者のみなさんと共有し、論じあいます。
企画発題者 後藤英司(横浜市立大学医学部)
発表者
大砂光正(横浜市立大学医学部)
郷真知(横浜市立大学医学部)
逆井清(横浜市立大学医学部)
白田祥子(横浜市立大学医学部)
中野渡雅樹(横浜市立大学医学部)
長堀まな(横浜市立大学医学部)
堀越理仁(横浜市立大学医学部)
横山千咲(横浜市立大学医学部)
学びをデザインする

学びとは、本来、自由な営みであるはずでした。ところが、学校教育の枠組みのなかで、いつのまにか学びは細分化され、専門教育に進むほど知も人間関係もタコツボ化している。タコツボにいったんおさまると抜け出せず、新たに入った人もいつのまにか出られなくなっていく。自由な営みどころか、まるで『山椒魚』のような悲しく恐ろしい状況ですね。ただ、タコツボにはタコツボの良さもある。今となってわざわざ壊してしまう必要もないと思います。そこで、少しスリムになってタコツボを自由に出入するために「学びをデザインする」という企画を提案します。「学びのデザイナー」のお話を聞きながら、私たちと一緒に「学びのデザイン」について構想してみませんか。さまざまな立場の方から、ご意見いただきたいと思います。
企画発題者 西岡亜紀(お茶の水女子大学)
話題提供者
野口香織(放送大学)
村山真理(お茶の水女子大学)
2010年12月4日(土)9:30 - 20:40
東京国際フォーラム
【口頭発表】
新材料開発における新規マネジメントモデル
林田英樹(大阪大学)
イノベーションを担う研究開発型スタートアップ企業の役割は大きいと期待されているが、電子材料の新製品開発については未だ十分 な研究がなされてこなかった。本講演では、材料系スタートアップ企業の成功要因モデルとして、電子材料系ベンチャー企業のケーススタディから、従来の研究開発 型ベンチャー企業によく見られるコアになる基礎技術もしくはアイデアを既に所有していて事業化を狙うというモデルではなく、事業 構想を含む正6面体マネジメントモデルを提案する。
受け手の視点 - プロジェクト研究への省察
長香奈恵(正会員)
2006年から2008年にかけて、構想学会でプロジェクトをテーマに研究活動を行う機会をいただいた。そこでは、プロジェクトという言葉の語義(pro+ject/前へ+投げる)について様々な考察を行うことができた。本発表では、投げるという行為を省察するため、受けるという行為についての考察を提示したい。この考察はユニヴァーサルデザイン(UD)研究における作り手と使い手の関係について考察を焼き直している。作り手と使い手の関係のはじまりには、作り手から投げられたものを使い手が受けるというきっかけがある。そこで、本稿では、「受ける」という行為に着目し、使い手の受信の経路とその特徴について考察を行う。
ジョイント・プロジェクト開発の新モデル構築の現場から ・・・中国映画産業における先進事例となる中・英共同プロジェクト構想具現化取り組みに参加して
加藤誠也(株式会社ダイナアーツ・インターディベロップメント)
安全保障および外交において日本と未だかつてない微妙なかけひきを続ける今日の中国。しかし、今やGDP世界第2位の経済大国と なった中国の実際には、世界に冠たる位置をほぼ確立した製造業の他にも胎動また成長著しい産業が多く見て取れる。その一つである映画産業は、 この5年間(2006-2010)で約4倍(391%)もの爆発的拡 大を遂げ(対して日本は過去5年間で同値は95%)、今後も加 速度的な成長が予想されている分野の一つである。日本の映画産業の現状はかつてのハリウッド物に代表される洋画の興行成績は前年割れ(前年比80%台)を続け、 視聴率を稼げたテレビドラマの映画化版を中心とする邦画が健闘しているものの、映画産業自体はもはや大きな成長が見込める産業ではなくなっ た。対して中国における同産業の成長は、そのほとんどが国内(中国および香港)資本および製作陣による作品により牽引されているものである が、この2年ほどを見るとその傾向に加えて洋画への需要が急速に高まり、今後はさらに成長が加速度的に見込ま れるものとなっている。こうした状況下、新たに、モチーフは清王朝末期のラストエンペラー治世下の1912?13年の上海を舞台 に中国人の多くの人たちに周知となっている実在の伝説的ヒーローの手記、脚本・監督はドキュメンタリ映画で高い評価を得ているエミー賞受賞者 でもある英国人、撮影チームは中国人と英国人を中心とした多国籍集団で・・・という企画に遭遇。日本からは小職 が、企画発案者より信託を得て、本企画のエグゼクティブ・プロデューサーという立場で、2010年9月、プロジェクト・ ボード(delegateorganization)をマカオおよび上海に開設し、それまで未定・不在で あったこの企画を実現するための仕組み・方法を具体化する取り組みを開始し、現在進行中。今般、単に映画という作品づくりに止まらず、その道 のプロである多国籍の関与者を得て本構想を具現化していく現時点までのこのプロジェクト・ディベロップメントの現場における試行錯誤の主たる ポイントを材料として報告させていただくことを通じて、これからのジョイント・プロジェクト開発のモデリングにおける主課題をご一緒に考えさ せていただきたい。
【 ラウンドテーブル 】
プラトン『クリトーン』について、およびコンテンポラリー・リベラルアーティスト・ソサエティ:

プラトンの初期著作『クリトーン』を素材に、その内容紹介をおこない、それにそくしたフリーディスカッションをおこないます。本著作は『ソクラテスの弁明』の続編として位置づけられ、死刑執行を待つソクラテスと彼の生涯の友クリトーンとの対話が記録されています。そこで主として展開するのは刑執行の断念を勧めるクリトーンに対するソクラテスのことば、関連して展開される法や美徳などのついてのコンパクトな対話です。
本ラウンドテーブルおしまいの30分は、日本構想学会の成果の継承について名乗りを上げたコンテンポラリー・リベラルアーティスト・ソサエティ: CLASについて紹介し、その構想について論じあいたく思います。企画発題・話題提供者 横山美鶴・半田智久(お茶の水女子大学)
『罪と罰』を読んで

F.M.ドストエフスキーの『罪と罰』を素材に、その簡単な紹介をおこないながら、この小説が扱っている主題に関連したいくつかの論点や構想を参加者のみなさんと共有し、論じあいます。
企画発題者 後藤英司(横浜市立大学医学部)
発表者
飯島崇善(横浜市立大学医学部)
石川優(横浜市立大学医学部)
岩屋毅(横浜市立大学医学部)
竹田雄馬(横浜市立大学医学部)
能條眞(横浜市立大学医学部)
濱中美希(横浜市立大学医学部)
本庄俊介(横浜市立大学医学部)
武藤智弘
ロールズ"正義"の構想を巡って

正義とは何か。わたしたちにとってはるか古く、そして新しい問いかけです。複雑高度化する現代社会のなかで、ことさら大きく社会構造の転換を余儀なくされる日本において、この問いはさらに重みを増して響いてきます。J.ロールズは、著作においてこの問いに真正面から論じ、後世に大きな論争を呼びました。彼の晩年に記された主著である『公正としての正義 再説』Justice as Fairness A Restatement (2001)から、彼の正義の構想に迫りたいと思います。J.ロールズの生涯及び著作に触れた後、ご参加の皆様と自由にディスカッションしたく思います。
企画発題者 猪岡武蔵(お茶の水女子大学)
知能環境論2010 : 3つのプロジェクトをベースに
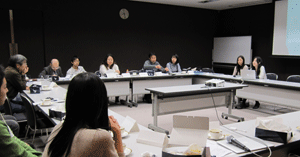
大学の知能環境論の授業で進めている3つのプロジェクト学習、(1)web上でのコンセプトミュージアムの構築に向けて、(2) 情報デザインに配慮したユニバーサル性のある電子ジャーナルの企画、編集、発行に向けて、(3)電子書籍の変遷とこれからの課題について、を紹介するとともに、それぞれの論点について参加者のみなさんと論じたく思います。
企画者・ 話題提供者 松田彩香(お茶の水女子大学)
高野明子(お茶の水女子大学)
瀬戸川友里(お茶の水女子大学)